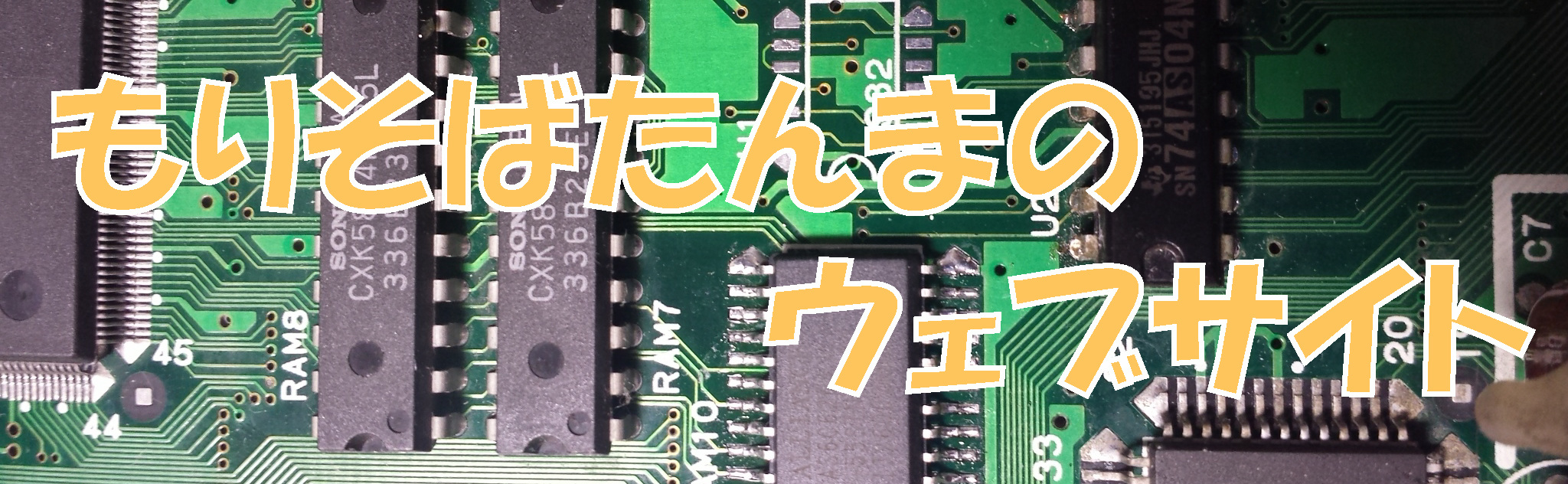サインボックス(マーキーライト)ってご存知でしょうか?
名前だけ聞いてもピンと来なくても、物をみたら分かる方も多いと思います。一般的な市販品ではアルファベットばかりなので、今回は100均で購入した部品をメインに、日本語(カタカナ)のマーキーライトを作ってみました。
文字はとりあえず「トイレ」という文字で作ってみることにしました。
(深い意味は無く、3文字くらいで作りたかっただけです)
タイトルに#1製作編としていますが、こちらは少し意味があり、これを改造して#2を作る事を計画中になります。
製作時間目安:1日~2日
(塗料やニスが乾くまでの間は待ち時間になるため)
もくじ
材料
| 品名 | 個数 | 単価 | 備考 |
| 木板 | 1 | 100 | サイズ45cm×15cm、キャンドゥ |
| 水性ニス | 1 | 100 | メープル色、キャンドゥ |
| ハケ | 1 | 100 | 30mm幅、ダイソー |
| 厚紙 | 1~2 | — | 0.7mm厚、今回は余り物を使用。 |
| アクリル絵の具 | 1 | 100 | マイルドグレー色、キャンドゥ |
| LEDライト6灯 | 3 | 100 | 文字の分だけ必要。キャンドゥ |
| 合板 | 1 | 100 | 30cm×45cm×3mm、セリア |
使った工具
| 工具名 | 個数 | 目安 価格 | 備考 |
| グルーガン | 1 | 200 | ダイソー製 |
| グルーガンスティック | 1 | 100 | Φ7.5mm、20本入り、ダイソー |
| アートナイフ | 1 | 400 | OLFA製。 |
| アートナイフ 替え刃 | 1 | 500 | OLFA製、25本入り |
| クラフトナイフL型 | 1 | 500 | OLFA製 |
| 糸のこ | 1 | 1000 | 適当に購入 |
※リンクはアマゾン内の各商品に飛びます。
※価格変動あるため、およその目安価格を表記しています。
木板のカット
今回、一文字を約10cm×10cm程度の大きさにしようとおもっていたので、木板を30cmにカットします。カットしたら、ニス塗りをします。
カット

ニス塗り

文字加工
文字の選択
切り出したい文字とフォントを選びます。私の場合は「トイレ」の三文字、フォントはフリーフォントの「ボスタスケテ」を使用させていただきました。
FONTS:
書体名:ボスタスケテ
著作権:きゃきらん さん
http://cute-freefont.flop.jp/baka_bosukete.html
同じ文字が良いという方(殆どいないと思いますが・・・)は、下にPDFファイルを入れてますのでご活用ください。
文字の切り出し
文字切り出しを行います。細かい文字なので、切れ味の良いペンのような刃物がお勧めです。カッターナイフでも良いのですが、厚紙が少々分厚いので多少力も入れることができるOLFAのアートナイフがお勧めです。(2019年5月16日では355円でした)

フチの台紙の切り出し、文字高さのマーキング
フチの台紙を切り出します。外周を全て個別に切り出しても良いのですが、そうするとグルーガンの使用量が増えるので、曲げていく方法で行っています。外周の長さを測って台紙を切っても良いのですが、足りない時に手間が増えるので、少し長めの45cmでカットしました。どうしても足りない場合は継ぎ足しでも大丈夫です。

高さを5cmで設定した理由ですが、LEDライトが首上が約1cm、首下が約3cmあるため、それぞれ5mmの余裕も勘案して5cmとしました。なので、1.5cmが文字の取り付けラインになります。

LEDライト取り付け位置の加工
LEDライトを取り付ける位置にLEDが通るように加工を行います。加工は穴でもいいですし、切り込みでもいいです。私は切り込みで行いました。LEDライトの位置は、適当に間隔を開けて、見た目が良くなると思う位置です。(結構適当です)

文字にフチを接着する
グルーガンを使って、フチを曲げていきながら、文字とフチを接着していきます。曲げが手間ではありますが、ここの出来は見た目に影響を及ぼすので、丁寧に行います。

木板の配線用の穴開け
文字が出来上がったら、木の板と合わせてみて配線を通す場所を決めます。通す場所を決めたら、ドリルで穴開けです。私の場合は10mmで穴を開けました。


文字の色塗り
文字にアクリル絵の具で色を塗ります。色はマイルドグレーにしましたが、概ね明るい色が合うと思いますが、何色でも構わないです。

文字にLEDの取り付け
キャップを全て外し、キャップを文字に取り付けて行きます。配線とLEDは木板を通してから文字(キャップ)に取り付けます。


文字と木板の取り付け
文字と木板をグルーガンで接着していきます。文字と文字の間など密集してて接着しにくい所がありますが、他の所がくっついていれば問題ないので、あえて難しい所は接着を行わなくても良いと思います。全周を接着させたい場合はグルーガンでは難しいと思いますので、他の接着方法をお勧めします。

裏箱の作製
裏側の箱を作製します。機能的には有っても無くてもいいので、合板を使用しています。10cmの厚みを持たせていますが、改造する時の事を考えて、だいぶ余裕みているだけなので、半分の5cmもあれば十分と思います。


裏箱のニス塗り
表の木板に合わせ裏箱もニスを塗ります。ポイントとかは・・・特に無いですね。ムラ無く塗れるように頑張るだけですね。

完成
これで、完成になります。電池BOXの固定は、後々改造をするので特に行いませんでした。

あとがき
余談にはなりますが、後々、ちょっと改造することを計画中です。お楽しみに。